
生食への切り替え方法 : 安全で確実なステップガイド
Table of Contents
愛犬のために私たち家族がしてあげられることと言えば、体に良いごはんを選ぶこと。
「このままドライフードだけで大丈夫かな?」
「生食のほうが無添加で自然に近いって聞くけど、本当にいいの?」
と、悩んでいる飼い主さんは多いはずです。
しかも、生食は「犬本来の食事」と言われる一方で様々な見解があります。
少しハードルが高いと感じてしまったり、なかなか踏み込めないこともあるでしょう。
そこで今回は、愛犬に実際に生食を与えていた犬の管理栄養士のわたしが、生食のメリットとデメリット、安全に切り替える方法をお伝えしていきます。
生食ドッグフードとは?愛犬に与えるメリットと効果

生食ドッグフードとは、犬の祖先であるオオカミの食事を再現した、犬本来の食のかたちです。
獲物を仕留め、その肉と内臓の内容物から栄養を得てきた犬のからだは、加熱調理されたドライフードではなく、生肉・内臓・骨・植物などを求めています。
そのため、生食のような自然素材のみで構成された食事は犬のからだに馴染みやすく、熱に弱い酵素やビタミンなどの栄養素も活用しやすい形で補うことができます。
添加物が気になる方や、食いつきのいいごはんを探している方、アレルギー対策をしたい方には特におすすめです。
ちなみに、生食はローフード(RawFood)とも呼ばれ、人でも生の野菜や果物を積極的にとり入れる食事法として知られています。
人も犬も同様に、美しく健やかな毎日を目指せるのが生食です。
メリット
1.食いつきの良さが期待できる
...食事が待ち遠しくなる生肉の香り
2.皮膚や被毛の美しさを維持しやすい
...自然に近い食習慣で腸内細菌のバランスをサポート
3.お口の綺麗さを維持しやすい
...自然に近い食習慣で口内細菌のバランスをサポート
4.うるおいのある毎日を維持しやすい
...ドライフードよりも水分摂取量が増やせる
5.体重管理がしやすい
...ドライフードよりも糖質が抑えられる
6.無添加でからだにやさしい
...添加物フリーの食事ができる
7.イキイキとした毎日を維持しやすい
...栄養豊富でバランスの取れた食事
実際に、生食を与えることでツヤのある毛並みや引き締まった筋肉を維持できたと感じている飼い主さんは、 94%を占めるというデータもある※1ほどです。
わたしも、長年生食で育った13歳のわんちゃんを知っていますが、歯が真っ白でピカピカでした。
もちろん、私の愛犬も生食が大好きです。うんちの調子も良く、食いしん坊な子ですが、少量でも満足のいく食事になっていたように思います。
生食を与えるときの注意点。愛犬の健康を守るために知っておくべきデメリット
犬の生食はメリットの多い食事ですが、生の肉や野菜を扱うごはんだからこその注意点もあります。
せっかく選んだ良質な食事が台無しになってしまわないように、また、生食の効果を最大限に得るために、デメリットについても理解しておきましょう。
生食のデメリット
1.衛生面に注意が必要
…適切に管理をして品質を保たなければならない
2.傷みやすい
…解凍後はすぐに使う必要がある
3.骨は消化器を傷つけたり詰まる可能性がある
…骨を含む生食では、与え方を守らないと体の負担となる
5.犬の体質によっては合わないこともある
…免疫力の低い老犬などには慎重に与える
生食はドライフードのように長期保存ができる手軽さはありませんが、わたし達飼い主が衛生面をしっかりと管理をすればデメリットを回避できます。
大切な愛犬のために少しだけ手をかけてあげて、美味しくからだに良いごはんを与えましょう。
生食への安全な切り替え方
生食へ安全に切り替えるには、今与えているフードに少量をトッピングするところから始め、7日間程度かけて生食のみに切り替えるようにしましょう。
突然、生食だけを与えてしまうと、食べ慣れないものにお腹がびっくりしてしまうこともあります。まず最初の2〜3日は、いつものフードの4分の1程度のトッピングからスタートすると安心です。
ただ、わんちゃんの体質は様々です。一度に切り替えてしまっても全く問題のない子もいれば、7日間では足りない子も中にはいます。
デリケートな愛犬にはスプーン1杯程度のトッピングからはじめるなど、愛犬に合わせて調整してあげるのがベストです。
生食を愛犬に与えるときの4つの約束

生食には注意点も多いですが、愛犬に合えばドライフードよりも美味しく、からだにやさしい食事と言えます。
安全に与えていくために、次の4つの約束を守ってくださいね。
- 信頼できるメーカーから購入する
- 生食の取扱い方を守る
- 生食の与える量を守る
- 生食を食べた後のうんちの様子を見る
信頼できるメーカーから購入する
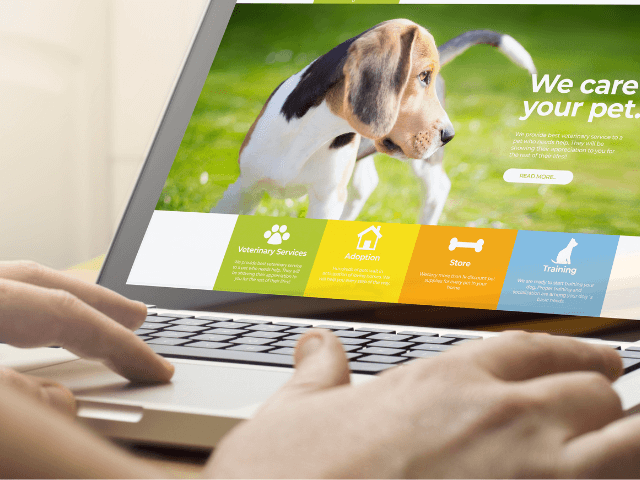
肉の質・製造工程の両面において、安全に管理された「生食用ペットフード」を与えるようにしましょう。
購入前にフードの公式サイトを確認し、信頼のおけるメーカーかどうかを判断することが大切です。
また、生食は肉だけではなく野菜や果物も含まれる栄養バランスのとれたものが理想的です。そして、そういった肉以外の食品の品質にも信頼がおけるものでなければ意味がありません。
必ず、安全性を保つための取り組みを公表している透明性の高いメーカーから購入するようにしましょう。
生食の取扱い方を守る
愛犬に生食用ドッグフードを与える前に、メーカーによる注意点・解凍方法・保存方法を事前に確認し、指示通りに行いましょう。
どれだけ高品質な生食用ドッグフードを選んでも、間違った方法で取り扱えば、からだにやさしい食事にはなりません。
どの生食にも共通するポイントをまとめました。
生食の取り扱い方
・購入後はすぐに冷凍庫へ。
…賞味期限がすぐにわかるようにおいておくと安心。
・使用する分を前日に冷蔵庫で解凍。
…商品によっては流水解凍OKのものもある
・解凍後、1度に与えきれないときは小分けにして冷蔵庫で保存。
…密封容器に入れて保存する。
・解凍した生食は2日以内に与えきる。
…できるだけ早めに消費する。
・再冷凍は1度まで。
…品質の低下につながる。
・食べ残しは破棄する。
…細菌が繁殖する可能性がある
また、FDA(アメリカ食品医薬品局)やCDC(アメリカ疾病予防管理センター)では、「生食を取り扱う際は顔や口元に手を触れないこと」と注意喚起をしています。
生食を適切に取り扱っていれば過剰に心配する必要はありませんが、飼い主さん自身が手洗いをまめに行い、食後は愛犬の顔を拭いてあげる習慣をつけておくとより安心できますよ。
少しの手間で美味しくからだに良い食事を与えられるのですから、難しくはありませんよね。
生食の与える量を守る

生食は栄養価が高く、与えすぎは消化不良や肥満のもととなるため、必ず愛犬に合う量を与えるようにしましょう。
給餌量は製品によって異なりますが、愛犬の体重を目安に調整していくものが多いです。
例えば、アニーズ・パントリーの場合は、健康な成犬なら体重の2〜4%程度が1日の量となります。子犬であれば体重の3〜5%が1日の量です。
ドライフードと比べると一見少なく見えますが、バランスのとれた食事なので栄養不良になることはありません。
私の愛犬が生食を食べていたときも、少量でも満足し、物足りない様子は見られませんでした。これは生食を与えたときだけに見せた様子だったので、とてもよく覚えています。
量ではなく質で満足できるので、食いしん坊のわんちゃんでも体重管理がしやすいでしょう。
生食を食べた後のうんちの様子を見る

これまでドライフードのような加熱食だけを食べていたわんちゃんは、生食へ切り替えることでうんちの状態が変わることがあります。
少量ずつ切り替えていけばお腹に負担はかかりづらいですが、硬すぎる便や軟便が続くときは、生食の量を減らして様子を見ましょう。
うんちの調子が戻ったら、より少ない量から慣らすようにしてみてください。
ただ、どうしても体質的に生食が合わないわんちゃんもいます。もし万が一、下痢が続くようなことがあれば、使用を止めて一度動物病院を受診しましょう。
人と同じように、わんちゃんにもそれぞれ体質や食の好みがあります。もし生食が合わなくても、焦らずに愛犬に合う食事をまた探してみてください。
生食は犬にとって栄養満点のごちそう!愛犬に喜んでもらおう
生食は衛生面の管理に注意が必要ですが、そのぶん生でしか得られないメリットがあるドッグフードです。
犬本来の自然な食生活は、健康維持に役立つだけではなく、愛犬にこのうえない満足感を与えてくれるでしょう。
まずは加熱食ばかりを食べてきたわんちゃんを、生食に慣らすことから始めてみてください。
急に生食に切り替えずに、トッピングから試すことで愛犬に負担なく与えることができますよ。
食材の品質と製造管理に信頼のおけるメーカーから購入する
使用するぶんだけ冷蔵庫で解凍。2日以内に与えきり、再冷凍は1度まで
生食を主食として与えるときは、愛犬の体重に合わせた2〜4%程度の量(健康な成犬の場合)
生食を食べた後に下痢や軟便にならないか確認しながら与える
生食を愛犬に与えた時のキラキラした瞳や駆け寄ってくる愛らしい姿は、いつ思い浮かべても私を笑顔にしてくれます。
皆さんの毎日にも、そんな瞬間が訪れるはずですよ。
※参考一覧
わが国における野生獣肉のペットフード利活用の現状と課題、Raw Pet Food - What is raw pet food(CDC)、The Canadian Veterinary Journal